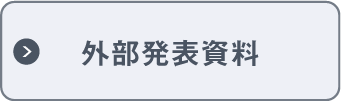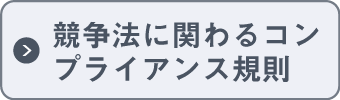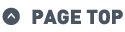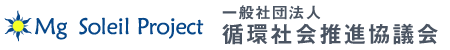循環社会推進協議会へのお誘い
応用部会長あいさつ
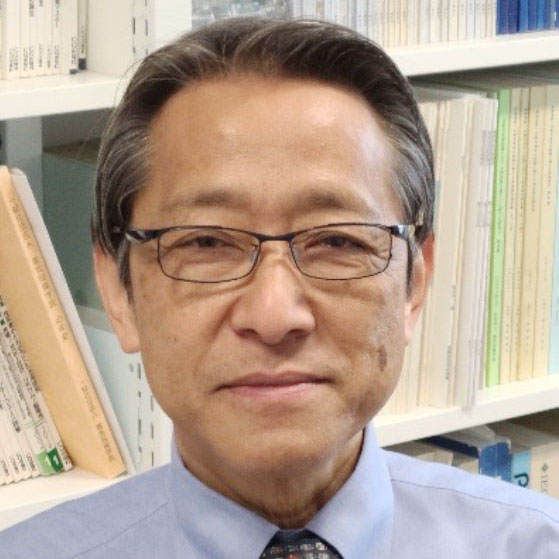
理事 兼 応用部会長
枡川 重男
東京電機大学 名誉教授
・電気設備学会会長
・電気設備学会会員、電気学会会員、IEEE LIFE メンバー
・パワーエレクトロニクス学会会員
私自身はこれまで学生教育とパワエレクトロニクスの研究を専門としてきました。マグネシウムと関連したことはありません。しかし,秋田県大潟村で開催されたソーラーカーレースのグリーンフリート部門に出場した時,玉川大学斎藤先生のチームがマグネシウム空気電池によるEVカーで参戦しているのをきっかけに,本協議会の前身であるマグネシウム循環社会協議会に参加しました。
マグネシウムは非常に軽い金属です。金の延べ棒サイズの鉄・アルミ・マグネシウムを手に取ると,“なんと軽い金属だ”と実感します。航空機,鉄道車両,自動車に利用すれば,CO2を大幅に削減できます。
マグネシウムは金属を製錬するときの触媒に使われています。さらに,電解液に食塩水を用いればマグネシウム空気電池になります。使用した後マグネシウムに還元すれば,電池の材料にもどります。食塩水を加えなければ電気を数十年備蓄することも可能です。平成30年北海道担振東部地震,東日本大震災,能登半島地震では,このマグネシウム電池が携帯電話の充電電源として活躍しました。しかし,マグネシウムはほぼ輸入に頼っていのが現状です。マテリアルセキュリティーの観点からは国内生産も検討すべきではないでしょうか。
一方,久米島で開催したMg Day in Kumejimaでは,離島のエネルギー問題を検討しました。島のディーゼル発電,太陽光発電,海洋深層水による温度差発電,蓄電装置,マグネシウム発電を組合わせた送電網を提案しました。送電網で使用するマグネシウムは海洋深層水の温度差発電や海ブドウの陸上養殖,車エビ養殖,化粧品等々,島の産業で利用した後に残る苦汁を製錬して作ります。製錬に必要な電力は送電網に設けた蓄電装置を使います。もちろん,蓄電装置の余剰電力は島の電気にも利用します。ベース電源として非常時の電源としてディーゼル発電機は残りますが,島の産業や家庭には環境に優しい電気を供給できるのではないでしょうか。
本協議会が目指す循環社会を構築するためには,マグネシウムの生産技術を確立すると同時に関連する企業の発展を図り,地域振興やカーボンニュートラルなど多岐に渡る課題に自治体や異業種の企業を結び付けて,解決の糸口を提案する活動を展開しなければなりません。例えば,CO2クレジット,太陽光パネルや有機廃棄物の再資源化,小型水力発電など課題は山積です。循環社会を目指して,様々な課題に取り組んでまいりますので,今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
お問い合わせ及び連絡先
事務局長
熊谷 枝折(代表理事)
電話:090-3752-0002
E-mail:s-kumagai@ksf@biglobe.ne.jp
開発委員会・事務局
前田 雅彦
電話:090-6945-1010
E-mail:maeda918@khc.biglobe.ne.jp
事務局
高田 賢一(不二ライトメタル(株))
電話:0968-78-2123
E-mail:ktakada@fujisash.net